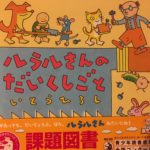国語が解けない理由の9割は読解力!国語の読解力がみるみる上がる読解テクニックとコツ 中学受験向け読解講座
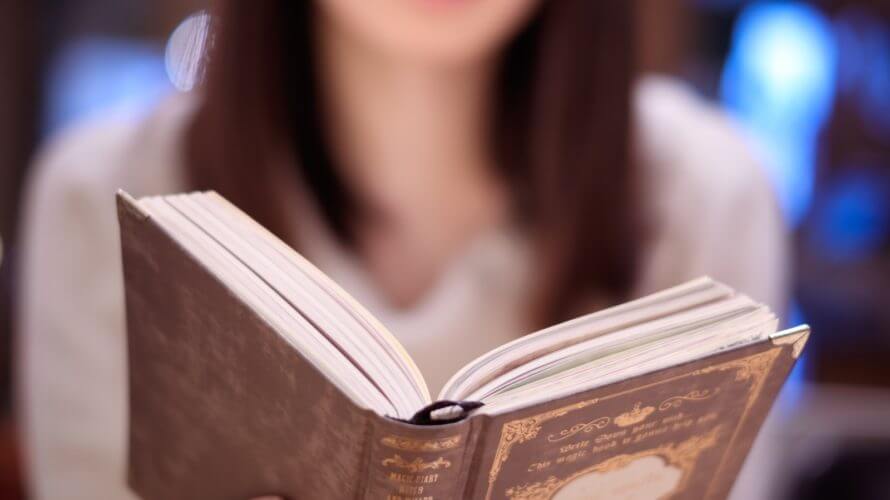
「国語を解くには読解力を鍛えると良い」
じゃあその読解力って何なのかという問いへの答えはおろか、核心である「どうやったら読解力が身につくのか」に至ってはほとんど語られていない「読解力」というオバケ。
こんな記事を見つけたので今一度読解力とテクニック、コツについて書いておきます。
東洋経済オンライン「私がどん底で見た「読解力がない」という地獄」
読解力の正体
読解力とは、文章を書いてある通りに読み、文章に書かれていることを把握及び文章に書かれていないことを論理的に推測する力です。
第一段階は文章を書いてある通りに読む力。
第二段階は文章に書いてあることを把握する力。
第三段階は文章に書かれていないことを論理的に推測する力。
文章を書いてある通りに読むのは日本語を知っていればできますね。ところが文章に書かれていることを把握できない子供が半分以上、文章に書かれていないことを論理的に推測できない子供が95%以上です。
だから、中学受験塾に通っている子供でも国語で60点とか70点みたいな中途半端な点数となります。
本当は国語は満点が取れて当たり前の教科です。ちゃんと読めば文章に答えが書いてありますし、答えを論理的に推測できるからです。
どうすれば読解力がない子供が読解力を身につけられるのか。
「読む技術」を身に付けるに尽きます。
「読む技術」養成のための学習方法
物語を読むための「読む技術」
転換点を見つけてください。
転換点とは主人公の行動様式や目的が変わるポイントです。
抽象的すぎて何なのか分からない方は以下を読んでください。
目的が転換点となる例。
行動様式の変化が転換点となる例。
主人公の行動様式も目的も変化しないが、周りが変化してしまう例。(難易度高め)
転換点とは急に主人公の行動様式や目的が変化してしまうポイントです。流し読みしていると気づきません。ましてや行動様式や目的の変化の背景にある心理の変化、状況の変化に気づきません。
逆に言うと、きちんと読んでいれば転換点と、その背景となる心理の変化や状況の変化に気づけます。
ではきちんと読むとは何なのでしょう?それは引っかかりを発見するための注意深い読書のことです。物語に対して感じる引っかかり=違和感は転換点の発見に大いに寄与するでしょう。
今までと違う行動をとったのはなぜだ?という引っかかりが違和感です。転換点の発見は引っかかりに気づくとも言い換えられます。
上で紹介した記事ではこんな風に引っかかりを表現しています。
② 英語の問題集で「I don’t like Ken, because he is always late for school.」を訳しなさいという問題があったとき
→字ズラを追っている子は「私はケンが好きではありません。なぜなら彼はいつも学校に遅刻するからです」と訳して、さっさと次の問題へ進む
→意味を理解する子は「遅刻するぐらいで、なんで人を嫌いになる必要があるんだ」と考えたりもしている
引用元 東洋経済オンライン 著者:石田 勝紀
普通に考えると、学校に遅刻するくらいで人を嫌いになるわけがないのになぜ嫌いになったのか、と疑問を持つはずです。
同じように英語の授業では奇妙な例文が頻出します。例えば、
Mary:Is this a pen?
Mike:No.This is an orange.
和訳します。
メアリー:これはペンですか?
マイク:いいえ、これはオレンジです。
これ、引っかかりませんか?普通の思考だったら引っかかります。するとこのポイントを中心に様々な疑問がわきあがります。
メアリーはオレンジをペンなのかどうか分からなかったのでマイクにペンなのかどうかを聞いた。するとマイクはオレンジだと言った。メアリーはペンとオレンジが区別できないほど耄碌している。したがってメアリーは認知に問題を抱えている。認知に問題を抱えているメアリーにマイクは、オレンジだ、と普通に答えた。もしオレンジをペンなのか?と聞く人がいたら、オレンジだ、と言う前に「どうした?調子が悪いのか?」と言うだろう。したがって、マイクはメアリーが認知に問題を抱えているのを当たり前として受け取り、回答したのだと考えられる。つまり、マイクとメアリーの関係は介護者と被介護者の関係である。
これが引っかかりに気づき、引っかかりから推測する思考です。
では、なぜ引っかからなかったのでしょうか?それは英文を訳すのが目的になっていたからです。例えば、ドラえもんがタケコプターを取り出して、のび太に「これはどこでもドアですか?」と聞いたら小さな子供でも「ドラえもんが狂ったのかもしれない」と考えるでしょう。
でも、英文を訳すのが目的になっていると「おかしい」という普通の感覚に気づかないのです。
読解力がない人は答えを出すのが目的になり、単に訳すだけなので引っかからないのです。答えを出すのに従順すぎるのです。
そういう引っかかり=違和感を感じるべきポイントこそが転換点によってもたらされているのです。
だから転換点に気づくべきなのです。
なぜ転換点にこだわるのか、理由は一つ。
転換点は違和感や引っかかりのきっかけとなった出来事や心理のもととなっており、それを答えさせる問題が多いからです。転換点における出来事や心理から違和感や引っかかりは論理的に導けます。
つまり、国語の答えを導けるのです。
論説文(説明文)を読むための「読む技術」
論説文(説明文)では以下の二つのパターンの文章しかありません。
1.条件を積み上げて結論を導き出すパターン
2.客観的事実を積み上げて結論を導き出すパターン
1は具体例をまだ挙げていませんが、2はどのように読み解くのか実例をもとに解説しました。
1について読み方を説明していきましょう。
1の文章は、作者が勝手に前提条件を与えてきます。
例えば、「世界とは人の認知しうる世界であり、それゆえに絶対的な存在ではない」みたいな感じです。
作者は必死になって、作者の考える前提条件を証明するための事実や論証を積み上げていきます。あるいは前提条件をもとに、ある解釈を証明しようとしてきます。こうした構造が分かっていると、1のパターンの中の文章が、前提条件を証明するための事実を述べているのか、あるいは証明するための論証なのか、逆に前提条件を強化するための反証なのかが把握できます。
前提条件を強化するための反証とは、あえて否定するために持ち出し、否定することで作者が勝手に設定した前提条件の正当性を強める役割を担っています。
引き立て役みたいな感じですね。
2は新聞の社説を解説していますので、読んでいただくとよく理解できると思います。
ポイントは事実と、事実に基づく作者の解釈を選り分けることです。そして、どの事実と作者の解釈が紐づいているのかを把握しながら、作者の結論を特定します。
2のパターンの読み方はこれだけです。
あとは接続詞に注意する等、細々としたテクニックがありますが、それは以下を読んでみてください。
読解力と「読む技術」
読解力を身に付けるのは根気が要る、と上の記事では書かれています。
疑問を持つ思考を常とするには、そのような習慣を身に付ける必要があるからです。
しかし、根気だけでは非効率的です。
だから、「読む技術」によって身につけた方が良いと私は考えています。
中学受験の国語の問題を解く上でやってはいけないこと
登場人物の気持ちに共感する
登場人物の気持ちは文章で書かれていることから論理的に推測するものであって、なりきったり共感するものではありません。
登場人物の気持ちになりきったり、共感したりすると、文章を無視した独りよがりの心理を想像する結果になるだけです。それは中学受験の国語においては確実に×となります。
小学校の国語の勉強と中学受験のための国語の勉強とで落差があるのはここだと思います。共感する読み方から、論理的読み方へのパラダイムシフト。
そのパラダイムシフトにすら気づかない子供が大半で、かつパラダイムシフトが起きている事実をきちんと教えない塾の姿勢は、大きな問題だと思います。
自分の経験に置き換える
自分の経験をもとに論理的に推測するのはOKですが、勝手に自分の経験に置き換えて文章を無視した読解をしてはいけません。
作者の生い立ちをもとに考える
作者の人格と著書物は切り離して考えてください。酒狂いで女狂いで暴力を振るう作者が、素晴らしい人格の主人公を描くのが文学の常です。
中学受験の国語においては書かれていることを把握し、書かれていないことを論理的に推測する能力が問われます。あくまで書かれていることがベースとなっているのです。
ですから、作者の生い立ちに関する知識は読解においては害悪ですので、捨て去ってください。
道徳的に正しいことが書かれていると考える
道徳的に正しいかどうかではなく、問われているのは文章に書かれていることから論理的に考えられるかどうかです。
例えば赤信号を渡ってはいけない、という社会的なルールについて、このような文章と問いがあったとしたらどうでしょうか?
文章
赤信号、みんなで渡れば怖くない。と、ある芸人は言った。本来は良くないはずの赤信号を渡る行為がここでは「怖くない」という言葉によって正当性を与えられ、善悪が逆転しているのである。ここでの善悪の基準は他者の視線であり、敷衍すると権力を持った存在による視線である。みんなで渡れば、一般的な判断基準では悪とされている行為の悪質性が矮小化され、しばしば逆転するのである。赤信号で停止する、その行為は善悪を判断する存在の判断基準によるものであり、絶対的な善ではなく相対的なものである。集団の判断基準は、集団がまさにそのように行動をしていることにより正当性を与えられ、一般的なルールに基づいた善悪とはまた異なった判断をするのである。
問い
赤信号を渡るのがなぜ悪いのかを説明せよ。
一般的なルールに基づいた回答
こちらが赤信号の時には車にひかれる可能性があるため危険であり、道交法に反しているからから悪い行いである。
文章に基づいた回答
赤信号を渡るのは悪いという判断基準が権力によって与えられているため悪い行いであるが、判断基準が変化すると悪い行いではなくなる。
読解力を身に付けるには
読解力はとても簡単に身につきます。
まずは文章に書かれていることのみ把握し推測しましょう。自分の気持ちや共感や作者の生い立ちや常識や道徳観、それらを捨て去りましょう。犬にでも食わせてやればいいです。
次に「読む技術」で構造化していきましょう。
すると、文章のみから主題が論理的に導き出せます。
そうした訓練を何度も行いましょう。そうするうちに勝手に読解力は身についてくるものです。
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

2018年課題図書「ルラルさんのだいくしごと」(ポプラ社)読書感想文5例 感想文から学ぶ読解 2018.08.16
- 次の記事

くもんのすいせん図書が凄い!幼児〜中学生までのおすすめ図書を完全網羅 2018.08.18