満点を狙う中学受験国語の具体的解法-アナと雪の女王を読み解く(後編)
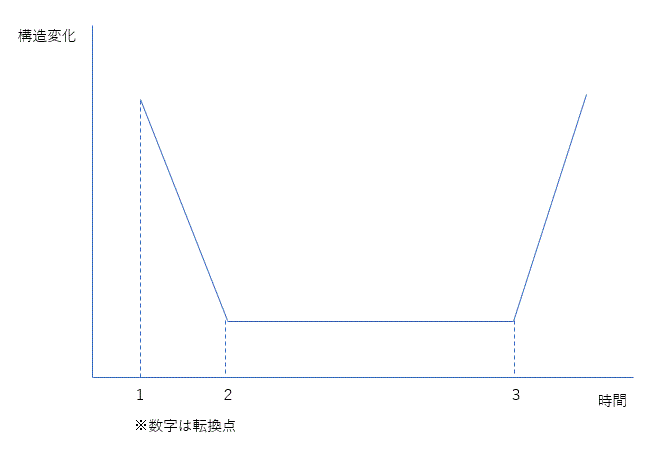
前回までのおさらい
詳細は前回を読んでいただければと思うのですが、さらっとまとめておきます。
物語の読み解き方
- 全体の構造を捉えることが重要です
- 構造は転換点によって形作られます
- 転換点の発見のため物語が変化したときの登場人物の行動に着目します
- 転換点となった行動の起点になった出来事を発見します
- 起点→行動→変化の一連の流れを捉え、変化の背景を把握します
- 転換点によって区切られた物語の変化をつなげたものが全体の構造です
物語の変化
- アナとエルサは仲よく遊び、そして王と王妃が存命の幸せな日々
- エルサは閉じこもるようになりアナと交流を持たなくなる。王と王妃は事故で亡くなる
- エルサが城から追いやられ自分の城を建設するが追っ手に捕らえられ、アナを魔法で凍り付かせてしまう
- 魔法を解除する方法を知ったアナがアレンデールをもとの姿に戻す
アナと雪の女王の転換点
- エルサが両親に魔法を禁じられ城の外に出ないように言いわたされ城に閉じこもる(1から2への転換)
- エルサがアレンデールを飛び出し自分だけの城を作る(2から3への転換)
- エルサがアナに抱き着きアナの魔法を(結果的に)解く(3から4への転換)
転換点の起点となった出来事
- エルサが自分の魔法でアナを傷つける
- エルサがアレンデールから追いやられる
- アナがエルサの魔法で凍りつく
起点→行動→変化
- エルサがアナを傷つけたことをきっかけとして、エルサはアナおよび他者と断絶する
- エルサがアレンデールから追いやられたことをきっかけに自分の城を作るが以前と同じようにアナを傷つけ凍り付かせてしまう
- アナが凍りついたことをきっかけにエルサがアナに抱き着きアナの魔法を解除する。解除する方法をしったエルサがアレンデールをもとの姿に戻す
構造
- アナとの交流がある幸せな日々
- 城に閉じこもる無味乾燥な日々
- 城から出てもまた新たな城に閉じこもり不安におびえる日々
- 自分の能力をコントロールする術を知ったことで他者との関われるようになり元の幸せな日々に戻る
構造を図にする
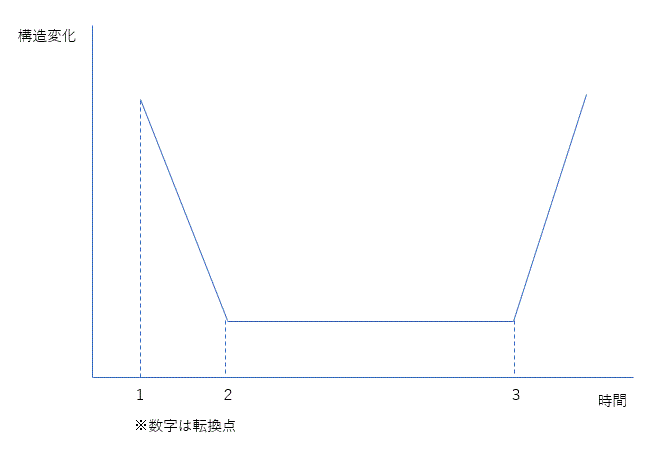
アナと雪の女王が物語としては面白くないと言われる理由
明白です。
上の構造図でも分かるように転換点1から転換点3までの間が長すぎるからです。
しかも転換点1から2の間と転換点2から3の間の構造の性質が同じだからです。
転換点1から2の間の構造:城に閉じこもる無味乾燥な日々
転換点2から3の間の構造:城から出てもまた新たな城に閉じこもり不安におびえる日々
抑揚がない物語は面白くありません。が、それは読解とは別の問題です。
さて、今回は前回の続きをやっていきましょう。
転換点2から3の間のエルサ
城に閉じこもっていたときと変わらないエルサ
前回も言いましたが、自分自身の能力をきっかけとしてアレンデールの城に閉じこもっていたエルサと、能力解放後自分自身の能力によって建設した城に閉じこもっていたエルサは、自分の能力によって自分を追い込んでいる点において全く変わりません。
レリゴーの歌では「一人のままじゃいけない」と言うものの現実は一人きりなのです。
アナが訪ねてきたときのエルサ
レリゴーの歌では一人きりの状況と能力を隠すことをやめようと歌っていましたが、アナが訪ねてきたときのエルサは、一人が心地よいから早く帰ってと言います。
これは本心でしょうか?
私は違うと考えます。
なぜなら、このセリフを言う直前にアナとの幸せな日々が一瞬脳裏をよぎるからです。しかし、次に何かを恐れ首を横に振ります。
エルサが心の奥底ではアナ(つまり他者)との関係を取り戻したいと考える根拠はここにあります。ところが何かが邪魔します。
それは何でしょうか?
自分の能力がまたアナを傷つけてしまうのが怖い気持ちです。
仲よくなりたい気持ちと、また傷つけてしまうのが怖い気持ちが相対して、ここでは傷つけてしまうのが怖い気持ちが勝ってしまい、「帰って」と言い放つのです。
そうしてエルサは怖さが勝ってまたアナを傷つけてしまいます。今度は頭ではなく胸、つまり心をです。
このあとアナとクリストフは謎の小人のもとに行きますが、謎の小人は「心に刺さった魔法は真実の愛じゃないと解けない」と言います。
さあ困りましたね。
ハンス王子の到着
ハンス王子たち一行が到着するとまずは城の階段下にいた雪だるまのお化けと戦うことになります。
雪だるまのお化けの攻撃の合間を縫って二人の兵士が城に侵入し、エルサを捉えようとします。
いえ、殺そうとしたという方が正確ですね。ボウガンでエルサを躊躇なく打とうとしているからです。
エルサは反撃しますが、とどめは刺しません。容易に二人の兵士を殺すことができる能力を持っているのにエルサはそれをしません。
これはエルサが自分の能力で人を傷つけたくない、と考えているからです。この考えに至った理由は幼少時のアナとの1件に由来します。
そうこうするうちにエルサは兵士たちに捕らえられてしまいます。
幽閉と脱出そして転換点3の到来
捕らえられたエルサはアレンデールの牢屋につながれてしまいます。その間にアナとクリストフが城に到着します。
彼らが城を目指した理由はアナの魔法を解くためです。魔法を解くのは真実の愛であり、それはハンス王子のキスだと信じているからです。
ところがハンス王子はアナに驚くべき告白をします。
自分がアナに近づいたのはアレンデールを乗っ取るためだ、と。絶望したアナは生きる気力を失います。
その間にハンス王子はアナ王女が死んだと言いふらし、エルサにもエルサの魔法のせいでアナが死んだ、と伝えます。
絶望したエルサがしゃがみこんだ隙にハンス王子はエルサを殺そうと剣を振るいますが、そこへアナが割って入り、その瞬間にアナの体が凍りつきエルサを守ったのと同時に自らは死に至ります。
このときエルサは物語の中で最大の変化を起こします。
アナに抱き着いたのです。
エルサはここまでの物語で誰とも接触しませんでした。幼少時のアナを除けば、交流を持つことすらしませんでした。しかしこのときは抱き着いたのです。これはすさまじい変化です。
さて、この理由を考えてみましょう。
エルサは心の奥底ではアナと仲良くしたかったことは前にも言いました。ところがそれをしなかったのは自分の能力でアナを傷つけるのが怖かったからです。
怖いという自身の感情が、アナと仲良くしたい本来の欲求に勝っていたのです。
仲良くしたいということはつまり、アナのことが好きということです。
アナを好きな気持ち(愛)が自身の感情(怖い)を上回ったのがこの時であり、怖いと思い抑圧してきた愛の感情をエルサは取り戻すのです。
これがアナに抱き着いた理由です。
そして、アナはエルサの愛で魔法が解除されます。
転換点3以降のエルサ
初めての他者との関わり
アナとの愛を媒介にした接触によりエルサは知ります。
愛によって自分の魔法をコントロールできる、と。
では愛ってなんでしょう?
ここで言う愛は自分よりも他人のことを思う心のことと推測します。
なぜなら、「自分の能力が怖い、人を傷つけないように人を遠ざけなくちゃ」という自分中心の思考が、「本来エルサが持っていた他人と仲良くして助けてあげたい(仲良くしたい)」という気持ちに変化した行動がアナの魔法を解除したのであり、後者を物語中では「愛」と言っているからです。
後者は他人のことを思う心に他なりません。
そして、アレンデールの人たちの窮状を助けてあげたいと思う「愛」の心がアレンデールに夏を取り戻すのです。
その後のエルサ
アレンデールの人々にスケートリンクを提供したり、オラフが溶けてしまわないように雪雲を提供したりします。明らかに行動が変わり、場面の雰囲気が変わりました。他人のことを思い、助けてあげる気持ちがエルサ自身の幸福をも招いたのです。
アナと雪の女王の主題
他者と関わりを持たなければ人間は幸せに生きていけない、これに尽きると思います。このメッセージを分かりやすく伝えているアナと雪の女王はクラシックに値する価値を持っていると思います。
ただ、面白さの点では途中で中だるみしてもいます。
「自分の能力によって自分自身を閉じ込めている」という構造が転換点1と2の間、転換点2と3の間で連続しており中だるみをもたらしています。
これは制作者のミスでしょうか?
私はそうではないと考えます。
他者と関わりを持たなければ人間は幸せに生きていけない、という主題をはっきりと伝えるためには、自分を認めるだけじゃダメなんだよ、と強調して伝えたかったが故に同様の構造を連続させたのだと思います。
まとめ
どうでしょうか。構造を把握するために転換点を探したり他色々したことで物語の意味をきちんと把握できたように思いませんか?
これを読む技術と言います。
文章では接続詞に注目したり、なんやかやするのが読む技術です。この技法は以前紹介しています。
小学校では読む技術の習得でなく、「感じる」教育が専らなされております。
「感じる」ことを私は否定しません。
が、「感じる」前の段階で物語を把握することが必要であり、それは読む技術を習得しなければできないことです。
ナボコフを読みなさいとか無茶は言いませんので、物語を読解しているときの思考に着目して欲しいと思います。
次回は「ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」を読解します。
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

満点を狙う中学受験国語の具体的解法-アナと雪の女王を読み解く(前編) 2018.07.19
- 次の記事

公文が中学受験に役立つ理由 学習習慣と正確な計算能力の獲得は弊害に勝る 2018.07.21

