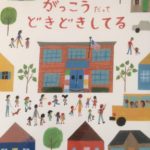映画「この世界の片隅に」あらすじ・解説(後編) 中学受験国語力養成講座

前回に引き続いて今回は映画「この世界の片隅に」を題材に物語の構造把握と主題を発見し、中学受験の国語力養成のポイントを解説していきます。
前回はあらすじと時系列に沿った解説、個人的な感想を書きましたが今回は中学受験対策用の読解に絞って書いていきます。
すずの行動様式及び心理の変化
すずの大きな行動及び心理的変化は物語の中で4つあります。
- 北條家に嫁いだ
- 水原くんとの再会で周作が好きだという本心に気づいた
- 晴美が死に自らの右手も失った
- 敗戦を知り押し殺してきた自分の感情が爆発した
これらの変化をもたらしたのは、それぞれ以下の通りです。
- 周作とその父がすずの実家に訪問してきたこと
- 水原くんが訪ねてきたこと
- 時限爆弾の爆発
- 敗戦
上記の4つの出来事が物語の重要な転換点です。
映画「この世界の片隅に」の構造
- 海苔農家の娘としての生活
- 知らない家に自分の意志も持たぬまま嫁いでからの生活
- 周作を好きだという本心に気づき北條家で生きることを自分の意思で決めた以後の生活
- 大切な家族だった晴美を失い、自らも右手を失った喪失感を伴った生活
- 敗戦以後の生活
映画はすずの生活、身の回りの出来事を淡々と描きますが、すずの生きている状況はすず自身ではなく他者や周りの環境の働きかけによって変わっていきます。
重要な隠喩「たんぽぽ」
すずのこうした変化、何かを思い出させませんか?
たんぽぽです。
たんぽぽの綿毛は自らの意志を持たず、風に流され、遠くの地に飛ばされて行ってもその地に根を張り、花を咲かせます。
たんぽぽをすずの生き方と重ね合わせるような描き方をしていることから、作者は「人の生とはたんぽぽのようなものである」と考えていると推測できます。
映画「この世界の片隅に」の主題
人はたんぽぽの綿毛のように、周りの状況や他者によって流されるように変わりゆき、それでいてしっかりと地に足をつけ、自らの意志で力強く自立し生きていく。
この物語は、周りに流されつつもしっかりと生きていこうとするすずの姿を通して、人の生の力強さを描いています。
近年私が見た映画の中では最高の映画です。やや大人向けですが、受験を控えた小学6年生の児童にも是非見て欲しいと思います。2時間くらい良い映画を見たってバチは当たりませんよ。
国語の読解手順(物語文)
まずは主人公の行動様式、心理の変化に注目してみましょう。
どの場面でどんな行動があって、どんな風に主人公の行動や心理が変わったのかを書き出してみましょう。
次に変化をもたらした地点(転換点)を境目として、物語を構造化してみましょう。
書き出した構造を見ながら、「この物語は何が言いたいのか」を考えてみましょう。
最初は主題が思いつかないかもしれません。しかし、それも訓練です。構造化するところまでは割と容易にできるようになるはずです。
何度も何度も練習して、しっかり主題を捉える訓練をするうちに必ずできるようになります。
長い小説を読む必要はありません。一番手っ取り早いのは塾のテキストに載っている国語の問題です。解こうとするのではなく、まずは上で書いたように把握するだけで良いです。
そうすれば自ずと問題にも正答できるようになっていますから安心してください。
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

映画「この世界の片隅に」あらすじ・解説(前編) 中学受験国語力養成講座 2018.08.09
- 次の記事

2018年課題図書「がっこうだってどきどきしてる」(WAVE出版)あらすじと読書感想文例 2018.08.11