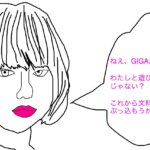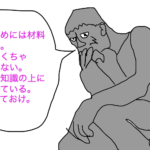【中学受験】終わらない宿題を終わらせるための意識改革
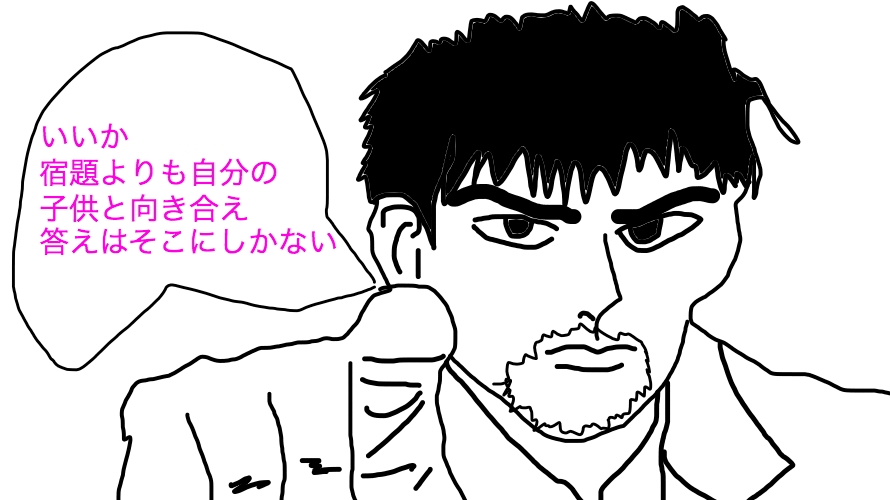
ハロー新小学4年生の皆さん!そして保護者の皆様方!今日も終わらない宿題で親子ともども枕を濡らしてますね!
グッジョブ!
それが普通です。
「うちの子がおかしいのかしら。それとも通ってる塾がおかしいのかしら」
と、疑心暗鬼になっているかもしれませんが、みんな同じなので安心するといいです。
入塾したてで皆さん面食らうのは宿題の量だと思います。
とくにこれまで学習系の習い事をやってなかったご家庭では親子ともども宿題の量に立ちすくみ、果敢に挑んでは、夜中の1時くらいに精根尽きて死んだように眠る、そういう日々を過ごされているのではないでしょうか?
もう一回言います。大丈夫です。そんなもんです、どこの家庭も。
だから毎日死んだように眠れ!Rest in peace!
って、まぁそれじゃ健康に良くないですよね。
なので今日はそんな宿題の山との関わり方についてやっていきたいと思います。
宿題に困っているのはあなただけではない
「今までプールとピアノしかやってこなかったのにいきなりこの量?しかもこんな問題を小学4年生がやるの?」
となるのは普通のことです。何もおかしくない。
でもよその家庭の事情を聞くわけにもいかず、自分の家だけがこの災禍に苛まれている、と思いがちですがみんなそうです。
もちろん公文やら学研といった学習系の習い事をやってきたご家庭も然り。
小学4年生ですとだいたい週2〜3回の通塾。それだけでも大変なのに加えて宿題が重くのしかかってきます。
真面目な親御さんほど「とにかく指示されたことはやらねば。何なら夜明けまで・・・!」と悲壮な覚悟でのぞみますが、子供は泣き出すし、自分も泣きたいし、それでいて大して成績は上がらない。
一体全体宿題ってなんなんだ?と思われているかと。
誤解を恐れずに言うと宿題ってのは塾にとっては保険みたいなものです。
授業中に全ての問題演習ができればそれにこしたことはありませんが、時間制限もありますしそうもいきません。
ただし、成績を上げて合格させるのが塾の使命。
そこで宿題というかたちを取らざるを得ないわけです。塾でやりきれなかった部分を家庭にゆだねていると言うと聞こえはいいですが、体のいい責任転嫁に近い。
まぁ、学習の定着のためには宿題と言う手段を使わざるを得ないという側面もあるのは事実ですが。
塾にとっては「何もしてくれないからうちの子の成績が上がらないんだ!転塾してやる!」ってな展開が嫌ですから、やるべきことを最大量提示することで義務を果たしているように見えると都合がいいわけです。
これが宿題は塾にとっての保険みたいなものと言った理由です。
実際のところ、宿題をたくさんこなしたからといってそれが学力と直結するかというと全然そんなことはありません。
重要なのは、課題意識と宿題に対する明確な目的を持つことです。
はぁ何それ?意味わかんねぇ!と思いますよね。
まぁまぁ、文句は続きを読んでからにしてくださいよ。
あるご家庭での出来事
小学5年生の家庭教師を受け持ったときのことです。
「塾から言われたことをちゃんとやっているのに最近成績が落ちてきて・・・。小学4年生の時は偏差値60くらいはあったのに今は50くらいまで下がってきていて。多分、うちの子集中力がないんです。それに塾の勉強も難しくなってきているし・・・」
ドラえもんのように青ざめた表情のお母様のお話を受けて、どんなことに取り組んでいるのかなーと思って見ていると、あるわあるわ宿題の嵐。基本問題、標準問題は当然のこととして応用問題、そして塾でやった内容の直しまで。
相葉雅紀(基本)に、櫻井翔(標準)に、えーとなんだ二宮(応用)?とにかく宿題の嵐なわけです。
で、本人はというとふざけているつもりはなく大真面目に取り組んでいる。
えらい。
でもバカだな、それが最初の印象です。
ひでー言い方だなと思われたかもしれませんが、なんで宿題やってんの?と聞いたときに、
「先生に怒られるから」
って。あぁ、もちろん先ほどのバカというのはお子さんに対してではなく先生に対してです。
人それぞれ理解度も違うし、苦手分野も違うのに画一的に宿題を最大量出してそれでいて業務をこなしている気になっている先生に対して心底アホだと思ったのを覚えています。
とりあえず基本問題をやらせてみると何とか解ける。ただ標準問題レベルになるとつっかえつっかえ。そして応用問題は頭をかきむしりながら「ねぇ、先生解答見ていい?」と聞いてくる。
「それいつもやってんの?」と聞くと恥ずかしそうに「うん」と。
で、なんとか宿題を終わらせて先生に怒られないようにしてるってわけですよ。
もうね、目的も手段も課題認識もグチャグチャ。こんなんで成績が上がるわけがありません。
客観的に見ると笑えるかもしれませんが、中学受験の沼におちいるとこういうことをあなた自身もしちゃいます。
げんに「ねぇ、ちょっと解き方教えてよ」と言われて、自分でも分からないから解答を見ながら「こうしてああしてこうやったら解けるでしょ」なんてやったことありませんか?
私が例にあげたご家庭と同類ですよ。
あのね、学習ってのは体系的なもんなんです。とくに算数はね。
例えばある問題が解けないとします。よく分からない親御様は解き方が分かれば解けるようになると勘違いします。そして解き方を教えます。ところがちょっと違う問題になるとまた解けない。
解けない原因は解けない問題のもっと前にあります。
どんなに難しい応用問題でもただの基本事項の組み合わせに過ぎません。
だから、例えば割合の応用問題が解けなかったとすると、
実際はそのもっと手前の割合(比べられる量、元になる量、割合)の概念があやふや
そして割合の概念のもっと前の分数、小数の概念があやふや
さらに遡って四則演算を正確にできない
もっと遡って問題文が読めてない
するとこの場合は問題文を読めるようになるところがスタート地点。そして四則演算。分数、小数の概念。割合の概念。と徐々に足元を固めていかないことには応用なんかいくらやったって意味がない。
宿題を全部こなすのは人間としてはえらいですけど受験生としてはちっともえらくない。
大事なのは自分の苦手を知って、克服することです。もっと言うと親がそこをフォローすることです。
いやぁ、そんなん素人だから無理っしょ!と思いますよね?
いえいえ、簡単な解決策があります。
とにかく例題をそのまま真似なさい
中途半端にできる子(偏差値50〜55くらい)ほど例題をおろそかにします。
「ふんふんふーん、このくらいの問題ちょろいぜ」と例題をすっ飛ばして自己流のやり方で類題を解いて、基本問題に突入します。
ところが自己流なのでちょっとひねった問題になると太刀打ちできません。
なぜなら基本がおろそかだから。
いいですか。
テキストの中で最も大事なのは応用(二宮)でも標準(櫻井翔)でもなく、例題(松本潤)なんです。
例題の解き方をそのまま真似てできるようになる。途中式をきっちり書く。図を書けと例題に出てたら愚直に図を書く。
そして例題の解き方そのままで類題を解いて、なんども反復して条件反射的に例題の解き方を再現できるようにする。そこから基本問題に取り掛かる。もちろん例題の解き方で解く。
「まなぶ」は「まねぶ」から派生した言葉であるように、基本的に学習っちゅうのは真似をして自分のものにするのが本質です。
応用問題は例題の解き方(=基本)の組み合わせです。
件の小学5年生については「とりあえず宿題は解答をうつしとけ」と指示をして、小学4年生のテキストを引っ張り出し、ひたすら関連分野の例題を真似て解かせました。
汚い途中式はきれいに書くように、図はグチャグチャ書かない、途中式は面倒くさくてもきちんと書く。
そこまでやってから今やっているところの例題をきちんと真似て解かせる。
応用問題?
そんなもんやらなくていい。
基本問題、欲を言えば標準問題まで解けりゃそれでいい。と割り切りました。で、テストは最後の大問2つ(応用レベル)はないものと思って、その前までの問題に集中しなさい、と。
テストは200点満点じゃなくて150点満点だ、と呪文のように言い聞かせましたよ。
結果、次のテストまでの1ヶ月程度で算数の偏差値が10上がってお母さんは大喜び。夏休みだけの短期契約でしたが継続を懇願されました。
しかしながらちょうどその頃好きになった子がいて私はその子のために生きると決意をし、泣く泣く継続拒否をしたのでした。割りのいい仕事でしたし惜しいなぁと思いつつ。
あ、でもその子とは3ヶ月で別れましたけど。
宿題は最大限の目安と割り切った方が良い
ってなわけでなぜ宿題を真面目にこなしちゃいけないのかはお分かりになりましたでしょうか?
宿題は最大公約数的な学習方法であって、個々のお子さんの事情や課題なんてお構いなしに課されるものだからです。
真面目であればあるほど宿題を終わらせることが目的になってしまい、学力には結びつかないんです。
だから、「宿題=やるべきこと」と思うのではなく、塾の先生の希望くらいに思っといたほうが精神的に楽です。
出される宿題をスラスラこなせるんだったらいいですが、小学生の子供が夜の10時以降、1時くらいまでかかりっきりになる状況は異常です。
睡眠は大事です。
宿題と向き合う上での具体的心構え
まず、習ってきたテキストの例題を真似させてみましょう。
真似できないんだったら基本がなってない証拠です。
真似できるまでやる。真似して類題を解く。
ここまでが第一段階。
これをクリアしたら基本問題を解く。
例題の解き方を真似して解く。
ここがクリアできなければ何度も基本問題を解いて学習を終了する。以降の宿題は答えを写す。
ここまでが第二段階。
ここをクリアできたら標準問題を解く。標準問題は例題そのままとはいきません。
多少ひねってあります。
でも例題がちゃんと解けていれば標準問題は解けます。解けないんだったらまた例題に戻る。そして例題の考え方を使えば解けることをお子さんが実感できればここはクリア。
にっちもさっちもいかないんだったらお母さん、お父さんが整理してあげる。あくまで例題の考え方を使えば解ける、という観点で。
え、そんなん無理?
だったら塾の先生に聞いたらいいんです。そのために高い金払ってるんですから。
ここまでがほぼ最終段階。
で、時間と余裕があったら応用問題に手をつけてみてくださいな。解けない?先生に怒られる?解答をうつせばいいんですよ。基本や標準と違って応用問題はちょっくらコツが必要ですから。
4年生、5年生だったら応用なんか解けなくてもどうせ6年生で嫌という程やりますから大丈夫です。
下手に応用問題に手を取られるくらいだったら例題(=基本)をしっかりやった方がいいです。
宿題に対する心構え
まぁ、気楽にいきましょ。
できる範囲でやりましょ。
とくに小学4年生はコツコツ地道に基本レベルを身につければいいんです。
そのうち花を咲かせます。
塾の宿題は大多数向けに与えられるものです。つまり、自分の子供の事情なんかお構いなしの課題です。
グーンと成績が伸びるのは偶然じゃありません。
自分の課題に気づいて(偶然も含む)、そこを埋めることができたときに「わかった!」となり成績が伸びるんです。
100人子供がいれば100人なりの課題があります。
そこに気づいてあげられるのは親御様しかいないんです。
宿題よりも我が子を見ましょうよ。それが宿題に対する意識改革です。
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

GIGAスクール構想って何?日本の公教育に何が起きているのか? 2021.04.02
- 次の記事

【中学受験】公立中高一貫校を目指すメリット、倍率、併願校について 2021.04.06