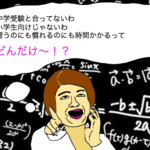【中学受験】5年生、6年生から伸びる子の特徴 偏差値別の対策
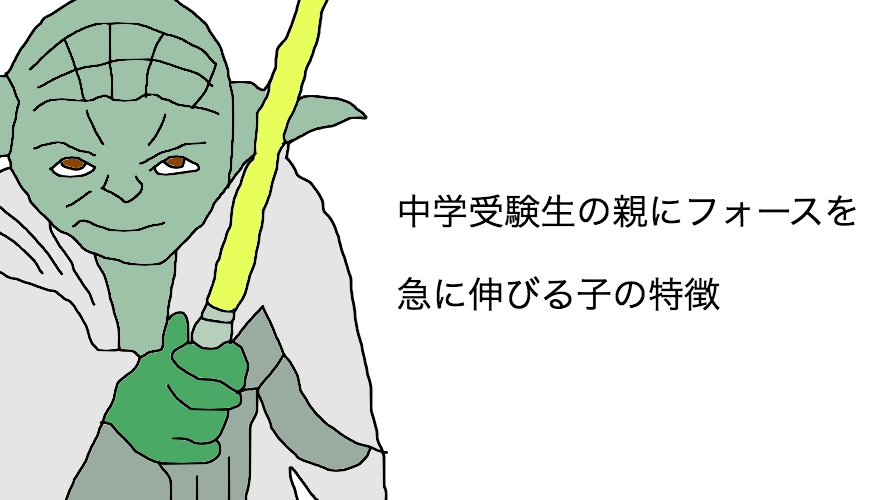
5年生、6年生で急に伸びる子にするために
親の正しい関与、家庭教師、転塾、3つの環境変化のうち、いずれかが急に成績が伸びる子に必要だと前ページで申し上げました。
で、それぞれメリット、デメリットがあります。
どれを実行するのか迷ってしまいます。
そこで私は、親の正しい関与からはじめてみては?と提案いたします。
理由はリスクとコストが低くて、すぐにやめられるからです。

そんなんやってるがな!
わわわ、そんなに怒らないでください。
まっさらな気持ちで今の関与が本当に正しい関与なのか一度点検してみてくださいよ。
「急に伸びる子」を実現する親の正しい関与①
ステップ1です。
まず、お子さんと同じ時間に起きて、同じ時間に寝てください。

本当にそれだけか?だましてないだろうな?
はい、だましてません。
だいたい、私がだましてどんないいことがあるんですか。

すまなかった。草葉の陰で見守ることにするぞ。
日本語の使い方間違ってますよ、とくみつさん。
それ、死んでますから。
「急に伸びる子」を実現する親の正しい関与②
ステップ2です。
お子さんが勉強している時はなるべく近くにいてください。
勉強を教える必要も、掛け声をかける必要もありません。
とにかく近くにいてください。
なお、親御さんが近くにいることによる学習効果向上はエビデンスによる裏付けもあります。
詳しく知りたい人は検索してみてください。
「急に伸びる子」を実現する親の正しい関与③
ステップ3です。
その場で丸付けをしてください。
丸付けのタイミングは早ければ早いほどいいです。
リアルタイム丸付けが最高ですが、できなければ少し遅れても構いません。
ただ、丸付けの効果はタイミングが遅くなればなるほど薄れていきます。
なるべく早めを意識してください。無理ない範囲で。
丸付けを習慣化するとお子さんの弱い部分と強い部分が見えてきます。
弱みと強みの把握から、正しい関与は始まります。
「急に伸びる子」を実現する親の正しい関与④
ステップ4です。
生活リズムをお子さんに合わせて、その場に居合わせるようにし、丸付けをしていると必ず質問がきます。
質問にはすぐに答えないでください。
分かっている親御さんほどすぐに答えを言ってしまいます。
ところが、人から言われた答えはすぐに忘れます。
自分で導き出した答えは記憶が長く定着します。
そこで、質問されたらこう返してください。

分かんないナー!どうしたらいいんだ?
みたいに質問に質問で返してください。
私も家庭教師をやっていたときはよく使っていた方法です。
さすがに「分かんないナー!」とは言えないので、「イイネー!で、どうしよっか?」と聞いてました。
頭の中の思考を言葉によって言語化するのは、学習の基本、つまり大事。
答えが返ってきたら「なるほど」と「いいね」しか言わないのもちょっとしたコツです。
「急に伸びる子」を実現する親の正しい関与⑤
ステップ5です。
スケジュールを作ってください。
スケジュールの作り方は↓で説明してます。
本当は先回りして問題を解いたりテキストを読んでおくといいんですが、余裕がない人は上のリンクからスケジュールの作り方のコツを読んでみてください。
ポイントは到達目標を明確にすることです。
到達目標は、組分けテストのクラスでもいいですし、合不合判定テストの偏差値でもいいです。
とにかくどこに到達したいのかはっきりさせてください。
5年生、6年生で伸びる子の特徴 まとめ
Q1:急に成績が伸びることはありますか?
A1:ほとんどない。むしろ期待しないほうがいい。
Q2:何をすると急に成績が伸びますか?
A2:急には伸びないが偏差値別に正しい方法はある。
Q3:急に成績が伸びる子の特徴は?
A3:環境変化。親の正しい関与、家庭教師、転塾のいずれか。
Q4:どの環境変化がおすすめ?
A4:リスクとコストが低いのは親の正しい関与。金があれば家庭教師。ギャンブラーは転塾。
さて、本日は他人のブログの口上やキャラクターをパクりつつ話を進めてまいりました。
パクったブログは中学受験100%ウカルログ(外部リンク)です。
私は日本中のほぼ全ての中学受験ブログに目を通していますが、このブログは記事の質の高さが群を抜いてます。
狂気の母親が娘を吉祥女子に導くまでのあれこれを書いておりますが、絵の巧さと文章構成が他のブログをぶっちぎってます。
しかも、狂気を装っていながら抜かりなく検索エンジン対策をしている周到さ。
たぶん、プロの犯行です。
ってわけでこれ読んでる全員、中学受験100%ウカルログを読んでくださいよ。
ちなみに私はこの人と何の関係もありません。
後日、この記事の続きとして親の関与についても書いております。
オーケイ、マッティオ。
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

【中学受験】中学受験で方程式って使っていいの?方程式を教えるデメリットはなに? 2022.05.28
- 次の記事

【中学受験】親のサポート 親ができることと親の役割 2022.06.06