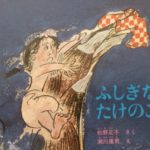くもんのすいせん図書「ごんぎつね」(あすなろ書房) 国語力養成のための超読解・解説
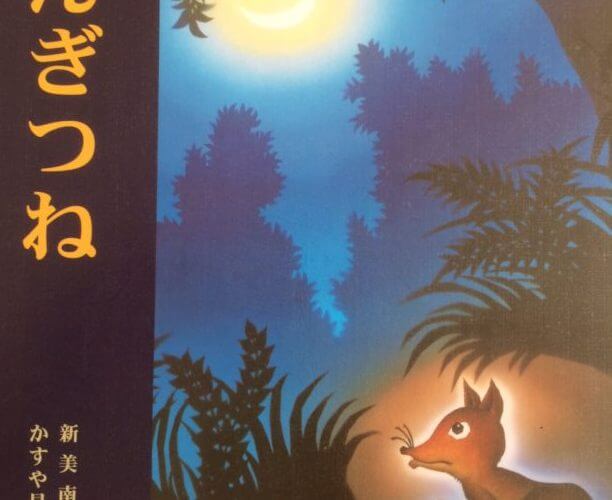
くもんのすいせん図書「ごんぎつね」(あすなろ書房 作:新美南吉 絵:かすや昌宏)の読解、解説です。
Dの1番ですので小学四年生向けの図書です。
ちなみに私が紹介するのはあすなろ書房の「ごんぎつね」で、公文では偕成社の「ごんぎつね」を推薦しています。
偕成社版の方は絵が実写的で、あすなろ書房版の方は絵がポップで漫画調です。
公文推薦
私の紹介
あすなろ書房版の方が絵がポップで読みやすいと思いこちらを取り上げました。
あらすじ
①ゴンが兵十の様子をうかがう
一人ぼっちの小狐「ごん」はある秋の日のこと、二、三日降り続いた雨がやむと川の方まで出かけていき、何人か人がいるのを見ました。そのうちの一人が兵十だとごんは気づきました。兵十は川でうなぎやきすを取っています。
ごんは兵十のことを知っています。以前にも何度か見かけて兵十だと知ったのでしょう。
他にも川で魚を取っている男はいましたが、ごんが真っ先に気づいたのは兵十です。
したがって、ごんは兵十をよく知っており、よく知っていることから何度も見かけられるような場所に住んでいるものと判断します。また、後でも明らかになりますが、ごんはこの村の住人をよく知っています。その中でもわざわざ兵十に注目したということはごんが兵十に何らかの感情を抱いている可能性が高いです。
②ごんのいたずら
ごんは兵十がいなくなるとちょっといたずらをしたくなり、兵十が取った魚を川に投げ込んでいきます。最後に太いうなぎを川に投げ込もうとしましたが、ぬるぬるしてうまくつかめず、うなぎが首に巻きついてしまいます。
その様子に気づいた兵十が怒鳴り立てるとごんは逃げていきます。巣穴の近くで首に巻きついたうなぎの頭を噛み砕くと、ごんは穴の近くの草の葉の上にうなぎをのせておきます。
③兵十のお母さんの葬式
10日ほど経ってからごんが弥助というお百姓さんの家の裏を通りかかると、弥助の奥さんがお歯黒をつけていたり、新兵衛の奥さんが髪を梳いている様子を見かけて「秋祭りでもあるのか」と思いますが、太鼓や笛の音がしないので訝しく思います。
観察するうちにごんは兵十の家の誰かの葬式だと気づきます。
葬式の列を見ていると、ごんは兵十の元気のない様子を見て死んだのが兵十のお母さんだと思います。そしてごんは考えます。兵十のお母さんが死ぬ間際に「うなぎを食べたい」と言ったから、兵十は川で漁をしていたのだと。
そして思います。
自分はそのうなぎをいたずらで取ってしまった、あんなことしなければ良かった、と。
ごんは葬儀の参列者の名前と奥さんが誰なのかを一目見て判別しています。村の様子に詳しいと考えられます。詳しいということは何度も村の様子を見に来ているという事実を示唆しています。だからこそ、最初の漁の場面で兵十に着目したのには何らかの理由があると考えられます。
うなぎを食べたいと兵十のお母さんが言っていたのはごんの想像です。したがって事実ではありません。どこにも兵十のお母さんがうなぎを食べたいと言っていたなどとは書いてありません。ところが、この想像がごんの運命を狂わせてしまうのです。
④ごんの「つぐない」
ある日ごんは麦をとぐ兵十の様子を見て、
おれと同じひとりぼっちの兵十か
引用元 ごんぎつね(あすなろ書房) 作:新美南吉 絵:かすや昌宏
と思います。
するといわし売りの声を聞いたごんは唐突にいわしをカゴから盗み、兵十の家に投げ込みます。
ごんはこう思います。
うなぎのつぐないに、まず一つ、いいことをしたと思いました。
引用元 ごんぎつね(あすなろ書房) 作:新美南吉 絵:かすや昌宏
次の日は山で栗を拾って兵十の家に置いて帰ります。兵十がいわし屋に殴られたのを知ると「しまった」と思います。何日も何日もごんは兵十の家に栗やら松茸やらを置いていきます。
「うなぎのつぐない」とごんは思っていますが、これは変です。「兵十のお母さんが死ぬ間際にうなぎを食べたいと言った」のはごんの想像でしかありません。だとすると何に対する償いなのかがよく分からなくなります。
ごんの主観に着目すると償いですが、客観的に見るとただ単に家に食べ物を置いていく奇妙な狐です。ごんの償いは事実に基づかないので、償っていると思い込んでいるだけです。しかも後ほど明らかになりますが、ごんは兵十にお礼を言って欲しいと思っています。
思い込みによる行為に対して見返りを求めていますので、いくら良いことをしているとはいえ、ごんの思考はストーカーの思考と同じです。
⑤食べ物が毎日置かれているのは何故だ
月夜の晩、兵十は加助に、お母さんが死んだ以後、なぜか家に栗や松茸が置いてある事実を告げます。兵十と加助は念仏の音がする家へと入っていきます。
兵十と加助が家から出て来た後、ごんは彼らの後を追います。加助は毎日食べ物が家に投げ込まれるのを「神様にお礼を言うといい」と兵十に言います。
ごんは、
おれにはお礼を言わないで、神さまにお礼を言うんじゃあ、おれは引き合わないなあ。
引用元 ごんぎつね(あすなろ書房) 作:新美南吉 絵:かすや昌宏
と思います。
ようやくごんの本音が出て来ます。「神さまに礼を言うんじゃ引き合わない」と思った場面です。ごんは償いをするため栗やマツタケを兵十の家に投げこんでいましたが、その実「自分がやっていることに気づいて欲しい」と考えており、更に言うと「自分の存在に気づいて欲しい」と考えていたのが明らかになります。
⑥ごんの死
次の日もごんは兵十の家に栗を持って出かけますが、ごんを見かけた兵十は「きつね」がいたずらをしに来たと思い、火縄銃でごんを撃ちます。銃で撃たれたごんを見ながら、兵十は土間に栗が置いてあるのを目にします。すると、兵十は気づきます。「毎日栗を持って来てくれたのはお前だったのか」と。ごんは目をつぶったままうなずき、兵十は自分のために毎日栗を持ってきてくれたごんを撃ち殺してしまったことに気づき、火縄銃を落としてしまいます。
完
最後の場面でようやくごんは報われます。兵十が自分の行いに気づいてくれたからです。
一人ぼっちで暮らしていたごんが初めて自分の存在意義に気づいてもらえたのであり、思い込みから端を発したストーカー行為が「人に気づいてもらった」ことにより報われた場面です。
しかもごんは何らかの理由で兵十に気づいてもらいたかったのだと考えられます。何人かが川で魚を取っている冒頭の場面でごんは兵十にのみ気づくからです。なぜかは作中では明かされませんが、ごんが兵十を意識しているのは明らかです。その兵十に自分の存在意義を気づいてもらえたので、殺されてしまったとはいえ願いが成就したと言えるでしょう。
物語の構造・要約・転換点
要約
いたずらでうなぎを取ってしまったゴンは、兵十の母親がうなぎを食べたいと言っていたから兵十が川に漁をしに来ていたものと想像し、償いのため兵十の家に食べ物を届けることにする。ところが、ごんの行いを知らない兵十によっていたずらをしに来たきつねと思われ撃ち殺されてしまう。
転換点
- いたずらをする
- 兵十の死んだ母親の言葉を想像する
- 償いのため食べ物を兵十の家に投げ込む
- 兵十が加助に話をする
- 兵十に気づかれる
読解のポイント
思いによる行動の変化
ごんの思いによる行動の変化が起点となって物語が変化していっています。
まず初めはちょっとしたいたずらをしたくなったこと。
次に母親を亡くした一人ぼっちの兵十を自分と同じだと感じること。
最後に自分の存在に気づいて欲しいという思い。
これら全てが自分の存在を誰か(特に兵十)に気づいて欲しいという思いから成り立っています。最後にごんが死ぬことによって兵十に初めて気づいてもらったのでごんの思いがかなったという意味でハッピーエンドです。
主題
奉仕によって、特別な感情を抱いていた他者に自らの存在が意識される喜び。=片思いの成就
これ、書き方を少し変えたら変態の物語になってしまいますね。
読み解くべき事柄
ごんは兵十だけに気づいた
最初の、何人かの人が川に行く場面でごんは兵十にのみ気づきます。兵十に何らかの感情を持っていないと兵十だけに気づくのは不自然です。何らかの興味を持っていたと判断できます。
ごんの想像と償い
兵十の母親がうなぎを食べたいと思っていたのはごんの想像に過ぎません。事実ではありません。ところが、ごんは兵十の母親がうなぎを食べたいと思っていたと想像し、償いのため食べ物を兵十の家に投げ込むのです。
ごんは兵十への償いから食べ物を投げ込むことにして、最終的には撃ち殺されてしまいます。
一方的に相手を思いやり、表面上は相手から裏切られてしまう構造となっています。これはストーカー行為であり、片思いに近いですね。この物語はごんの兵十に対する片思いが物理的には成就しなかった過程を描いていると判断します。
ただ、精神的にはこの片思いは成就します。
神さまに礼を言うんじゃ引き合わない
ごんの兵十に対する片思いの物語である決定的な証拠です。
「神さまに礼を言うんじゃ引き合わない」とごんが思ったので、心底では「自分に礼を言って欲しかった」つまり、「自分の存在に気づいて欲しかった」と考えているのが示唆されています。
一方的な兵十に対する思いは最後に撃ち殺されてしまう出来事により物理的には成就しませんでした。
しかし、ごんが「誰かに自分の存在を気づいて欲しかった」という思いが最後に叶ったので、幸せな物語として捉える方が理にかなっていると思います。
ごんぎつねの原作
実はこのバージョンのごんぎつねは教科書版です。他に原作版があります。
その原作では、兵十が「いつも栗をくれたのはお前だったのか」と問う場面でごんは、
原作版:嬉しくなった
教科書版:うなづいた
引用元 ごんぎつね 作:新美南吉
とあります。
だいぶ違いますね。原作版は死の間際でも兵十に気づいてもらえたのを嬉しくなったと言っており、教科書版では単なる肯定で終わっています。
また、償いに関する場面では、
原作版:何か好い事をした様に思えました。
教科書版:うなぎのつぐないに、まず一つ、いいことをしたと思いました。
引用元 ごんぎつね 作:新美南吉
「つぐない」という言葉が明らかに付け足されています。
読んでいて「つぐない」が引っかかって仕方がありませんでした。物語の後半のごんの思い(俺にお礼を言え。俺の好意に気づけ)と「つぐない」が不整合を起こしているからです。
というわけで、この書き換えを行なった人物はおそらく「ごんぎつね」を、償いの気持ちが成就しなかった悲劇の物語として書き換えたかったものと判断できます。
しかし、物語を読んでいくと上記の意図とごんの気持ちが不整合を起こしており、「つぐない」が浮いてしまっています。
とはいえ書き換えられた物語であっても書かれている文章のみから読むことが大事です。「原作版では実はこうだった、だから教科書版でもこうだ」という読み方は読解の作法からすると外れていますので、知識として知っておくに留めておきましょう。
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

くもんのすいせん図書が凄い!幼児〜中学生までのおすすめ図書を完全網羅 2018.08.18
- 次の記事

くもんのすいせん図書「ふしぎなたけのこ」(福音館書店) 超読解・解説 2018.08.19