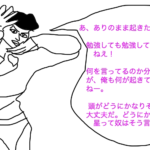【中学受験】私立中学・高校で上位10%以内の成績だった人の思考と勉強法
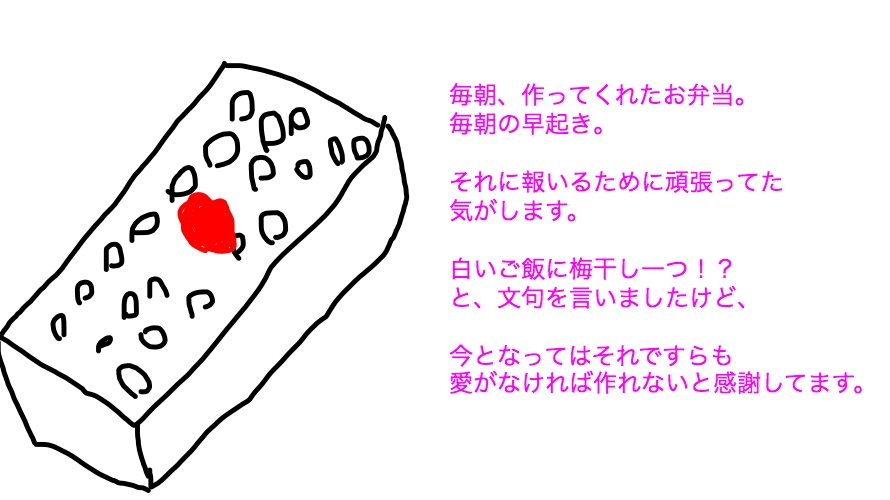
一昨日、私立中学で成績不振にならないためにというテーマで書きました。
んで、これから入学を控えた小学6年生のお子さんと親御様にもう少し詳しく努力と成績の関係、そして頑張ることを継続できた理由なんぞを書いていこうと思います。
さて、おさらいですが、私立中学に通って成績不振にならないためには、
「努力して学年の10%以内に入り続けること」
「中学1年生で10%以内に入ること」
と書きました。
よくよく読んでみますと当たり前ですよね。
運動不足にならないためには運動するのが大事、みたいな何の役にも立たないアドバイスをしているように読めるのではないでしょうか。
ちょいと角度の違うお話をいたします。
私は上位陣がなぜ上位陣でいられるのかが不思議で、色々話を聞いてみたり、何をやっているのかそれとなく尋ねたりしたものです。すると、一様に彼らは言うんです。
「普通に授業受けて普通に復習して、テスト前はザーッと総復習するだけ」
って。
めっちゃ普通。
てっきりね、私、ブブカしか乗り越えられないようなバーを乗り越えて学年10番以内に入っているのだ、という経験談を聞けるのかと思ってましたよ。
まさに金メダル級の必殺技、鳥人間、波動拳みたいな学習法を期待してたんですけど普通のことしか言わないんですよ。
逆に私も何をやっているのか尋ねられたりしましたよ。見た瞬間に記憶できる特別な頭脳を持っているのでR!と答えたい気持ちやまやま、嘘を言うわけにもいきませんので
「いや、普通にやってるだけなんだよね」
と答えたものです。
私や他の上位陣も含めて、一つも嘘をついておりません。
普通なんだけどねー、って。ともすれば超嫌味に聞こえるかもしれませんが、本人たちにとってみるとけして特別ではない努力の積み重ねでして、
「ワタシ、フツー、オーディナリーピーポー」としか答えようがないんです。
では、一体上位と下位では何が違うのか?
お気づきかもしれませんね。
上位陣と下位陣では普通の基準が違うんです。
例えば歴史の勉強。
私にとっての普通は板書したノートの事柄を全て覚え、それらの事柄を関連づけて「どうしてそんな出来事が起きたのか」「なぜこの人物はそのような行動をとったのか」をストーリーにして頭に叩き込むことでした。
これを話すと下位陣にはめちゃめちゃびっくりされたんです。
「それ、普通じゃねーよ」
と。
歴史だけではございません。数学も、現代文も、化学も、地学もぜーんぶこっちが思ってる普通と、下位陣の普通の基準が違う。
これが「普通」という言葉の奥行きの深さでございます。いろんなものを包み込んでいるわけですね。
ところが、最初から基準が違ってたわけじゃないんです。だってそうでしょ。入学した時はだいたい同じくらいのレベルなんですよ。そして中学で習う内容も全員ヨーイドンですからね。
それなのになぜ普通の基準が違ってしまったのか?
答えは最初の中間試験と期末試験にあります。
中学1年生、最初の中間試験と期末試験
中学入学後、初めての試験、すなわち中間試験。5月の終わりくらいにやるアレです。
初めての試験、それも私立中学での試験、いやが応にも緊張感が高まります。こいつらはどれくらいの実力なのか、普段はアホそうに見えるけど実はすごいんじゃないか。
実を言うとちょっとビビってました。ちびりそうでしたよ。実際ちびってたかも。
てなわけで、私は初めての中間試験に向けていっぱい勉強をしました。競争に勝ちたいとか、人を出し抜きたいとか、そんな理由ではなかったです。
ビビってたのと同時に毎朝、早くに起きて弁当を作ってくれる母を少しでも笑顔にしたかったからです。
子供ながらに念願の志望校に合格しなかった事実に負い目を感じていました。母の落胆する様子も見ていましたし、そうさせてしまった自分がひたすら不甲斐なく、せめて入学してからは母に笑顔でいてもらいたかったんです。
どんな努力をすればいいのか、全ての問いに答えるためにはどう勉強すればいいのかを考えて勉強し、のぞんだ中間試験では学年で上位10%以内に入りました。
「おお、やればできる!」
一番驚いていたのは自分です。どう勉強すれば上位に入れるのかが分かったのもこの時。上位10%に入るための勉強の基準が見えたんです。
努力と上位10%に入るための関係性が垣間見えた瞬間です。
次は期末試験。
中間試験で行った勉強の仕方をなぞりながら、もう少し深いレベルまで理解しようと試みる。
すると、中間試験以上の成績が残せたんです。
「おお、ここまでやると上位5%に入れるのか」
努力の基準値が見え、その基準値を少し上げるための工夫をすると嘘をつかない結果がかえってきた。
そうなるとあとは自分のさじ加減次第で成績を決められる。
下位の人、もしくは中位の人は私を含めた上位陣が、まるで頭がいいとか特別なことをしているように思ってました。
そして袋とじでも開けるかのようにどう勉強しているのか聞いてきたんです。
でも返す言葉は「普通に勉強しているだけ」
成績上位陣は例外なく努力の基準値が高く、「普通」の基準が高かったんです。
上位と下位の違いは普通の努力の違いだけ。そう、普通の基準が違うだけ。
私は気づきました。
成績の良し悪しは頭が良いかどうかじゃなく、基準値が高いかどうかである、と。
最初の中間試験、期末試験で頑張ると良い理由
私の経験則だけで話を進めています。個人的な体験だから一般化できないよねー、と思う方は別に読まなくてもいいです。
私は成績不振に陥りたくなければ、最初の中間試験、期末試験は死に物狂いで頑張った方がいいと経験則で申し上げます。だって、逆転した人見たことないもん。とくに学年上位10番以内なんて最初の中間試験、期末試験のメンツからほぼ3年間変わらなかったんですよ?
だから成績不振にならないためには最初の中間試験、期末試験は頑張った方がいい。
ちなみに成績不振に陥った人がどうなったかもお話ししましょうか?
ついていけなくなって退学になった人もいます。学校来なくなった人もいます。留年した人もいる。
そうなりたいですかって話です。
「最初から頑張らなくても2学期、3学期もあるわけじゃん?」
と仰いますかね?
いやいやいや、最初に頑張らなかった人ってその後も頑張ってないですから。
それに、最初の中間試験や期末試験は簡単なんですよ。
基本事項ばかりだから点数も取りやすい。これが中学2年生、3年生にでもなってご覧なさいよ。1年生の時の知識や理解を前提にした問題が出てきますよ。中学1年生の時の理解が浅かったらどうします?1年生の勉強からやり直すんですか?
それってハンデ戦ですよ。逆ハンデ。上位陣はさっさと目の前の勉強に集中しているのに、理解が甘かったせいでやり直さざるを得ない。そしたら今やってることに時間を十分に割けないですよね?
したがいましてそれまできっちり勉強してこなかった人、基準値の低い人が、最初にきっちり勉強して理解をしちゃってる人に追いつくには2倍、3倍の労力が必要です。だから、最初からきっちりやっとけばいいんです。そのほうが難易度が低いんです。
いいから、入学後の中間試験、期末試験はきっちりやっとけ。
そう申し上げたい。
中学、高校は勉強だけのためじゃないと言う方に
成績の話ばかり私はしてきましたので、こんな反対意見もあろうかと思います。
「中高は勉強だけじゃなくて好きなことを見つけたりするための時間じゃないの?」
まさにそうです。中高は勉強だけの時間じゃありません。好きなものを見つけてとことん打ち込めばいいんです。
けどもね、これも経験則で言いましょう。
好きなことにめちゃくちゃ打ち込んでる生徒って大抵成績良かったんです。体育会系であれ、文化系であれ。
勉強にもその他のことに対しても一所懸命やってたんですよ。
自分を裏切らない努力の仕方を知っているから。
うしろめたさを感じずに好きなことに打ち込めるから。
努力を積み重ねたおかげで好きなことに打ち込める時間ができたから。
いろんな理由があると思います。
学校っていうのは基本的に勉強をする場所です。私立中学、高校であればなおさら。その基本がブレブレなのに、他のことに対して真っ当に打ち込めるのかってわけです。
足元がしっかりしているから踏ん張れる。
スタートダッシュが肝心。まずは最初の中間試験、期末試験を頑張ってみましょう。
頑張って結果を残すことができたら自分の目線は意識せずとも高くなっているはずです。
「普通」に頑張る基準が人よりも高くなっているはずです。その時は気づかなくてもね。
そしたら是非とも自分自身の「普通」を育てて大きくしていってください。
すごいところにたどり着けるはずですから。
最後に言いますよ。いいですか。
一周以上遅れた地点から逆転する方が難しいんです。
難易度の低いうちに自分の目線を上げておきましょうよ。その方が簡単ですよ。
困難は目を背けると、より大きな困難になってかえってくるものですから。
Self-assigned task piled on the desk of good works
Knowing hardship appreciate the best of both worlds!
(対訳)
自ら背負い、机の上に積み上げられた良き仕事
自らの意志で背負った困難は、素晴らしい世界を教えてくれるんだ!
quotation from:Luv(sic) pt.2 by nujabes
R.I.P. nujabes
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事

【中学受験】私立中学で成績不振に陥る生徒がいるのはなぜか 最初の1年が鍵を握る 2019.03.18
- 次の記事

【中学受験】国語の成績を上げるための基礎能力を要素分解して解説する 2019.03.26